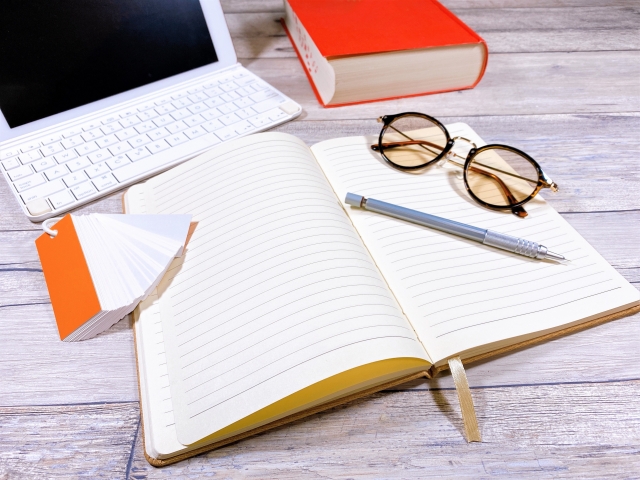独学で中小企業診断士に1発合格するための勉強法

中小企業診断士の資格に挑戦しようと思っているのですが…
いいですね。今、中小企業診断士は注目されている資格です。
コロナの影響もあってたくさんの補助金が出ていますが、中小企業診断士は補助金獲得の際に必要な事業計画作成を支援できるので、中小企業の社長さんから期待を寄せられているんです。
そうなんですね!
独学で取りたいのですが可能でしょうか?
サラリーマンなので時間があまりとれないのと、お金もかけられないので…
中小企業診断士の江﨑と申します。
この記事では、中小企業診断士の資格を取りたいけど、独学で何とかならないかと考えている方に対して、率直な意見をお話しさせていただきます。
私は2008年に独学で中小企業診断士試験に合格し、約10年は企業内診断士として活動していました。2019年に独立開業し、いまは補助金獲得支援を中心とした、事業計画作成の支援業務を行っています。

1.中小企業診断士に独学で合格は可能か
結論としては可能です。現に私は独学で合格していますし、独学で合格している人はたくさんいます。ではなぜ、「独学で合格したいんだけど…」と悩んでしまうのでしょうか。
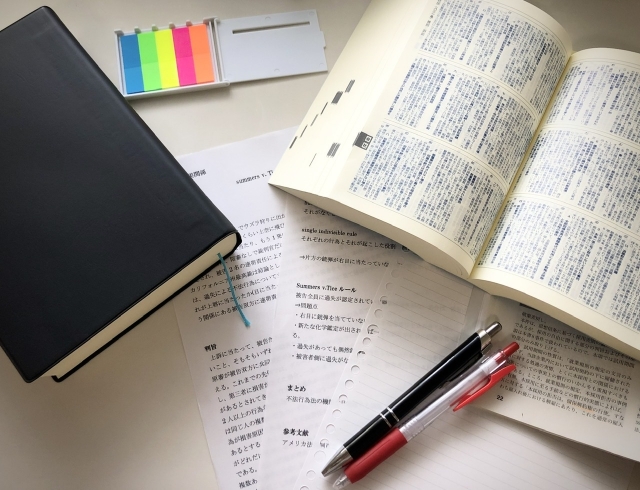
独学で合格することは可能
いつでも好きな時間に勉強ができて、参考書代だけで合格できる独学。「独学で合格することは可能だから独学で合格しよう」という話であれば誰も悩みません。独立で合格が難しい理由というのがあり、その理由を解決する手段を求めてこの記事にたどり着いたのだと思います。
独学が難しい理由には以下のようなものがあります
- 自分をコントロールできず勉強をさぼってしまう
- 参考書を読んだだけでは理解できない
- どういった教材を選べばいいのかわからない
- 効率的な勉強の仕方がわからない
この記事ではこのような問題を解決する方法を考えるともに、特に「効率的な勉強の仕方」についてフォーカスをあてて記載していきます。
独学で試験合格する難易度とは?
- 学習時間は800~1,000時間程度(1年間毎日2~3時間勉強すると受かる程度)
- 仕事を辞めるほどではないが趣味の時間を全て捧げる程度の覚悟は必要
独学で試験合格する難易度がどの程度かというのがよくわからない人のために、難易度について説明しておきます。中小企業診断士試験の概要をある程度調べてみるとわかりますが、この資格は1次試験と2次試験に分かれており、科目も多岐にわたっています。
試験内容は、超難関資格である弁護士・公認会計士・税理士・司法書士といったほどではありませんが、簿記一級や行政書士といった資格に比べるとはるかに試験の工程も複雑で難しい資格です。
学習時間は800時間~1,000時間程度と言われており、一年365日で合格するためには毎日休みなく2~3時間程度は勉強しなければいけない計算になります。
上述の超難関資格クラスになると無職になって一日中勉強してという生活を何年かという人もいます。それほどではなく、働きながらでも取れなくはないけれどもプライベートな趣味の時間をすべて勉強にあてるぐらいの覚悟は必要になります。
独学に向いている人と、向いていない人
中小企業診断士の勉強の仕方について説明する前に、そもそもやめておいた方がいい人というのがあります。向いている人の説明とともに先に説明しておきます。
独学に向いている人
独学に向いている人は以下のような人です。
- すでに前提知識がある程度ある人
- 自分なりの勉強法を確立できている人
すでに前提知識がある程度ある人
私が独学で合格できたのは、私が公認会計士だからです。公認会計士は勉強の範囲が中小企業診断士と被っており、財務会計・経営学・経済学・会社法といった科目があります。さらに、前職はITコンサルタントで経営情報システムの導入に関わる仕事をやっていました。
「なーんだ、それなら当然取れるよね」と思われたかもしれませんが、大事なことはこの「当然そうなるよね」という状況に、いかにもっていくかです。合格には必ず理由があります。
ついでに書くと、「公認会計士という上位の資格を持ってるなら中小企業診断士になる必要はないんじゃ…」と思われた方もたくさんいると思いますが、それはただの先入観ということを私は今実感しています。というのも「中小企業診断士」だから仕事を依頼されているケースが急増しているからです。
公認会計士と中小企業診断士の難易度の違いなんて中小企業の社長さんには関係がなく、大会社がメインターゲットの公認会計士は中小企業の社長さんには全くなじみがありません。逆に「中小企業診断士=補助金の専門家」というイメージがコロナ禍により飛躍的に定着しました。
話がそれましたが、すでに前提知識があれば独学でもテキストを読んだだけで「ああ、あのことか」とすぐピンときます。学習効率は段違いに高く、合格も現実的です。
自分なりの勉強法を確立できている人
独学は、想像以上に険しい道です。しかし、独学でどんなに難しい試験にも合格してしまう人もいます。天才だからという言葉で片付けてしまうのは簡単ですが、そういった人たちに話を聞いてみると「なるほど、それなら当然そうなるよな」と思わされます。
毎日10時間勉強しても疲れない人だったり、非常に効率的にスキマ時間を利用していたり、何らかの必勝パターンを持っていたり、様々な理由がありますが全く何の理由もなく合格している人はいません。
理由もなく合格しているように見える人は理由を忘れてしまっているのか自分で気が付いていないことがほとんどです。普通の人ができないことを「え?みんなやってないの?」という感じで特に気にもせずやっている人がたまにいます。
そういう人の話を聞いていると、「そりゃこの人は受かるわ」と思ってしまいますが、そういう状況に自分を持っていけなければ合格は難しいです。合格者が百人いれば百通りの「そりゃ受かるわ」があります。あなたにも必ずあります。
独学に向いていない人
独学に向いていない人は以下のような人です。
- 全く関係ないことを仕事にしている人
- 自分との約束を守れない人
全く関係ないことを仕事にしている人
中小企業診断士の試験科目は経営全般に関係している多岐にわたるものです。そのどの科目とも関係しないことを仕事にしている人は独学に向いていません。すべての科目を一から実務の経験もなく勉強するのは非常に時間もかかりますし、イメージもできなくてつらいです。
自分との約束を守れない人
「○○をやるぞ!」と誓ったことをなんだかんだ理由をつけて反故にしてしまう人は独学はやめた方がいいです。100%とは言いませんが、80%ぐらいは守れる意志が必要です。1日1時間は勉強すると誓ったら何が何でも1時間勉強するという気概が求められます。
何をやればいいのかがはっきりして、この日にはこれをやるというのが決まったとしても、それを守る力がなければ目標は達成できません。
受験勉強に関わらず、自分との約束を守るというのは幸せになるためにはとても大事なことです。目標を達成することができるかどうかは、ほとんどこの「自分との約束を守れるかどうか」にかかっています。
が、多くの人がないがしろにしています。これを機に、「自分との約束を守れる自分になる!」と決心して独学の道を進むのもいいかもしれません。
「自分は典型的な向いてないタイプだ…」と思った方は独学はあきらめて、きちんとしたカリキュラムが組まれている専門学校の講座を受講することをお勧めします。専門学校の講座は無理なくできるようにスケジュールが組まれていますし、みんなやっているという強制力が働くので独学よりはるかに合格に近づけます。
合格できなければ意味がない
知識ゼロでやる気が全然ない人でも独学で合格できる方法ってないんですか
合格するにはちゃんと理由があります。相談者さんの質問はA地点からB地点へ移動するのに瞬間移動する方法ないですか?と聞いているのと同じです。ないです。
独学で楽に合格する方法を教えてもらえると思ったのに…
例えば、お金をかけてタクシーを使う(講座を受講する)、徒歩で何時間もかける(独学)という当たり前の方法がまずあります。
何時間も歩く中で楽に歩く靴を手に入れる方法であったり、方角を間違わないコンパスを手に入れる方法であったりはあります。そういったことは教えられます。
しかし、何時間も歩くというのは変わらないわけです。瞬間移動は頭の中では想像できますが、現実にはありません。それと同じです。
独学における瞬間移動という超能力を身に付けるために何年も無駄な努力を繰り返して結局フェードアウトしていった受験仲間もいます…
独学で合格したいのはなぜでしょうか「可能な限り楽に(時間的・経済的負担を軽くして)”合格したい”」からじゃないでしょうか。
知識ゼロの人が独学で挑むと、楽どころか相当に時間的な負担がかかります。結果的に、何年も合格が遅れます。教材代は少額で済むかもしれませんが、1年で数百万円稼ぐことも可能な中小企業診断士の資格で、3年遅れると3年分の年収を失うことになります。
最初の3年ではありません。最後の3年分の年収です。もしあなたが中小企業診断士として最終的に年収1千万円になれたとしたら(十分可能です)3千万円以上の損失になります。
これって、本当に時間的・経済的な負担が軽くなっているでしょうか?
自分との約束を守れない人が独学で挑むと合格できる可能性は限りなくゼロになります。
大事なことをはできる限り最短で効率よく”資格を取る”ことです。最高効率を求めた結果、何年たっても合格できないのでは本末転倒です。
2.独学で試験に合格するための勉強法
独学って難しそうですね…
私としては、お金はかかったとしても通信講座を受講することをお勧めしたいところですが、どうしても独学でというなら効率的に勉強していく必要があります。
それでも独学は可能ということもわかりました。何とか独学で合格する方法を教えてください!
独学で合格する人には必勝パターンがあるというお話をしました。ここでは公認会計士・中小企業診断士に合格した私が難関資格を取得するにあたってポイントだと考える方法を公開します。
作戦Ⅰ:独学なら過去問を中心に据える
試験に合格するためには、「試験に出題されること」を頭に入れる必要があります。試験に出題されることを体系にまとめているのがテキストであり、参考書です。
しかし、体系的ではないものの、もっと試験に出題されることをダイレクトに教えてくれる教材があります。それが過去問です。
「過去問に一回出た問題なんだから、もう出ないんじゃないの?」と思っている時期が私にもありました。この発想は出題者の気持ちを全く考えていません。
あなたが中小企業診断士だとします。「先生、次回の試験問題を作成してください」とお願いされました。断れない状況です。どうするでしょうか?
私であれば、まず過去問を研究して、「なるほどこういう風に問題を作るのか…、この問題はいい問題だな、この問題は何を問いたいのかよくわからないな」といった感じで評判のよかった問題を真似して作ります。
当然、主題範囲は似通ってきます。多少数字が変わったり、切り口は変えないと全く同じ問題は出しにくいですが、問いたい主旨は変わりません。中には、「これは中小企業診断士になる以上絶対に答えられてほしい」と感じる問題であればそのまま同じ問題を出します。
こうして、過去問というのは最も出題されやすいポイントについてまとめてある最高の教材になっています。問題作成者がこれを参考に作っているのだから当然です。
作戦Ⅱ:覚える対象を絞り込む
過去問の有用性がわかったら、どのように過去問を利用するのかという話になります。具体的な手順を説明します。
①試験の概要を把握する
まずは、試験にどういう科目が出るのかぐらいは把握しておきます。このタイミングで参考書を一式選ぶのもいいでしょう。過去問を中心に据えますが、過去問は体系的な整理がされていないため、体系的に整理されている参考書は必ず必要です。
参考書を選ぶにあたってはカラフルとか図表がたくさん使われているとかそういった要素が注目されますが、私独自の観点からは以下のポイントに注意する必要があります。
余白がある
この後説明しますが、参考書にはかなりいろいろ書く必要があります。そこで書き込む余白がない参考書はお勧めできません。
目次がわかりやすい
参考書がどのように体系化されているかは目次を見ればわかります。目次のタイトルがやたらと長かったり、数が多すぎたり、ぱっと見頭に入りにくそうだったらやめるべきです。
②まずは過去問を1回解いてみる
この時点では全く何の勉強もできていないので、過去問を解くというよりは問題を読んで答えを見るといった方が正しいかもしれません。時間を計って本番と同じ条件でやってもいいですが、要はどんな問題が出題されているのかを実際に目で見て確認する必要があります。
ここでは、4,5年前ぐらいの過去問を使います。最新の過去問は最後に本番に近い条件で予行演習用に使うので取っておきます。
③目次を覚える
ここからが本格的な独学の始まりですが、まず選んだテキストの目次を暗記します。この時、「3.最短で合格するための勉強テクニック」で説明する方法を利用することで比較的短期間に忘れないような方法で暗記することが可能です。
目次を暗記するのは、試験に必要な知識の全貌を把握しておくためです。これによって、必要な知識の抜け漏れを防止することができるようになり、試験中に「この話は参考書には載っていなかったから答えられなくてもいい」ということが瞬時に判断できるようになります。
完全に暗記できないと次のステップに進めないわけではなく、ある程度大項目(1科目10項目程度)のレベル感で頭に入れば次のステップに進み徐々に深いレベルまで覚えていきます。
④参考書を読む
ここからテキストの読み込みが始まります。ステップ数としては4番目ですが、ここまではそこまで時間がかからないはずです。ステップ②の過去問の確認がある程度時間がかかりますが、読んで答えを見るだけならそれほど大変ではないと思います。
本番はここからで、まず一通り参考書を読んでいきます。意味が分からないところもたくさんあると思いますが、とりあえず最後まで読みます。この参考書は何度も何度も読むことになるので、最初はあまり気負わずにわからないところはどんどん飛ばしていいです。
そして、いわゆるスキマ時間、移動中や手待ちの時間などに目次を思い出しながらその目次のパートに何が書いてあったかを思い出すようにしてください。誰かに説明することを想像して思い浮かべると効果的です。
最初は漠然とで大丈夫です。それを繰り返していると全く説明できない所と、簡単に説明できるところがわかってきます。全く説明できないところは理解ができていない所です。理解ができていない理由は何かがわかっていないからなのですが、これについては「3.最短で合格するための勉強テクニック」で説明します。
⑤過去問を解く
テキストの内容を一通り読んだ段階で、再度過去問を解きます。最初にやった問題を今度はちゃんと時間を計ってやってもいいですし、別の過去問を時間を計ってやってもいいです。
「そんなまとまった時間はない!」ということであればちょこちょこ空いた時間で1問づつ解いてもいいです。時間を計ってやるのは、「こんなに時間がないのか…」という事実を実感し、ペース配分を掴むためです。何もやらないよりはどんな形であれやるべきです。
最初は全く時間も足りず、何のことやらわからない問題だらけだと思いますが、徐々に理解を深めていければ問題ありません。
⑥参考書に出題された問題を書き込む
過去問を解き終わったら、参考書の該当箇所を見つけてその余白に「こういう問題が出題された」「こういう風に間違えた」など、過去問の内容をメモします。これによって、参考書の該当箇所を読むときにどういう風に問題が出されるのか、自分がどういうところで間違えやすいのかというのを思い出せます。
この作業を何度も繰り返すのですが、やっているとやたらと集中する個所や全くメモがされない個所が出てきます。これがそのまま、どれだけこの試験において重要な個所かそうでもない個所かの判断基準になります。
「いったいどこに書けばいいんだ?」という問題もあると思います。そういう問題はテキストの範疇から外れた問題なので、答えられなくても問題ありません。ただ、簡単にそう思わずに、テキストのどこかには結び付けられるように真剣に考えてみてください。
⑦テキストを回す
メモしただけで満足してはいけません。このメモによってオリジナルの参考書ができてくるのですが、そのテキストを何度も繰り返し最初から最後まで目を通し続けます。受験生はこの作業の事を「テキストを回す」といいます。テキストを読めない時は暗記した目次を思い出しながら参考書の内容を思い出します。
⑧⑤に戻る
ここまで来たら、⑤に戻って次の過去問を解きます。過去問を解くタイミングは例えば1ヵ月に1回とか、ある程度期間をあけてもいいですし、最初の時期に3年分ぐらいを残して一気に解いて参考書に該当箇所をメモして早めにオリジナルの参考書を作り上げてしまってもいいです。
私が1年間でやるのであれば、例えば10年分の過去問があったとしたら、10年前~5年前の過去問を最初の3ヵ月うちにやって、4年前、3年前を6ヵ月後、2年前を9か月後、1年前を11か月後といったぐらいの配分でやります。
3.最短で合格するための勉強テクニック
2.で大体の勉強の流れについては説明しましたが、この項目では勉強するうえでのテクニック的な話をさせていただきたいと思います。

いつでもどこでも何もなくても勉強できる!
道を歩いているとき、満員電車に揺られているとき、寝る直前、参考書を開いて読むことができないシチュエーションはたくさんあります。そういう時に参考書を頭の中で読む方法があります。
「え?そんなことができたら試験に参考書持ち込んでいけるようなものじゃないか!」と思われたかもしれませんが、その通りです。この方法が極まるとテキストを持ち込めることになります。ただ、たった数ヵ月でそこまで達人の域に達するの無理でしょうからせいぜいテキストの項目ぐらいが限度です。
そろばんの達人がものすごい桁数を暗算で計算してしまう芸がありますが、あれに似ていて訓練次第ではそんなレベルに達しますが誰でも簡単にそこまでできるといったものでもありません。
「場所法」-古代ギリシャからある最古にして最強の記憶術
その方法とは、場所法という記憶術です。原理は簡単で、あなたが日常的に目にしているもの家の中、学校までの道のり、会社までの道のり、散歩しているコース等々
①そこに何があるか何も見なくても思い出せる
②思い出せるものに順序をつけられる
この2つを満たす何らかのものに結び付けてものを覚えていく方法です。例えば、私の家から最寄り駅に向かうにあたって、ご近所さんの家が何件かあり、広場があり、交差点があり、坂道があり…と頭の中でそのコースをイメージすることができます。
その映像を忘れることはありません。この映像に覚えなければいけない項目をこじつけで結び付けていきます。できるだけ荒唐無稽なものの方が忘れにくいです。まず最初に家からスタートするいくつかのコースを設定して、科目ごとの参考書の目次を場所に結び付けていきます。
そして、場所を思い出しながら目次を思い出してみます。思い出せなかったらイメージのインパクトが薄いのでもっと変なイメージで結び付ける必要があります。
目次を場所と一緒に思い出せるようになったら、そこからさらに細かい情報を思い出すべくイメージを膨らませていきます。
テキストが頭の中にあればいつでもどこでも勉強できる
テキストの目次を場所法で記憶するだけでも、勉強しなければいけない範囲を網羅的に抑えることができます。実際にやってみるとわかりますが、それだけでかなり安心感があります。
一度目次が頭に入ったら、まずはそれを時間があるときに何度も反復します。テキストを見なくても思い出せるようになっていれば、「時間がある時」というのは大幅に増えます。テキストを見ないと思い出せないのであれば、ちゃんと腰を落ち着けてテキストを開く場所が必要です。
歩いている時間、寝る直前、ほんの数分の待ち時間…このような時間にはテキストを開くことができません。また、ちゃんとテキストを開く時間があったとしてもテキストそのものを持ってきていなかったら開くことができません。
頭の中に目次があるだけで少なくともそういった「テキストを開かないと目次を思い出せない人」との間に圧倒的なアドバンテージが生まれます。
場所法によって目次だけではなくさらに詳細まで思い出せるようになれば、テキストを持ち歩かないと思い出せない人に比べて、利用できるスキマ時間が大幅に増える=勉強時間が大幅に増えることになります。
試験中こそ本当に効果を発揮する
頭の中でテキストをある程度再現できるというのは、試験中にこそ本当に効果を発揮します。
瞬時にアクセスできるテキストを持ち込んだようなものだから当然と言えば当然なのですが、そこまで詳細に記憶できていなかったとしても「この知識はテキストには載っていなかった(だからわからなくても問題ない)」というのが即判断できるという点は試験本番では非常に重要になってきます。
正答率が低い問題にはできるだけ時間をかけず、誰もが正答できる問題を確実に回答するというのは、全ての試験において重要なポイントです。この見極めを「テキストに載っている知識で解けるか解けないか」で判断する際に、テキストを網羅的に頭に入れていることが役立ちます。
ノートは作らない
「場所法でテキストを記憶する」という作戦を採用するのであれば、ノートを別に作るのは得策ではありません。というのも、記憶する場所がテキスト用とノート用で別に必要になるからです。
場所法において、記憶できる容量は記憶している場所に比例しています。使う場所をできるだけ消費せずに記憶するためには、記憶するポイントはできるだけ少なくしておいた方がいいです。
「ノートを作らずにどうやってまとめればいいのか」という問題ですが、ノートではなくテキストの余白に記載します。したがって、教材としては書きこめる余地がたくさんあるテキストの方が理想的です。ノートを取る必要もないぐらいよくまとまっているテキストであればなおいいでしょう。
ノートを別に作るデメリットはもう一つあります。それは「すでにテキストに書いてあることをノートにもう一度書かなければいけない」という点です。それによって覚える、記憶が定着するというメリットももちろんありますが、場所法にそれは不要です。
とにかく短い時間で効率よく勉強するということを追求するのであれば、テキストに書いてある内容をノートにもう一度書く時間はもったいないですし、結局そのノートもテキストより自分用にカスタマイズされているとはいえ取り出して眺める必要があります。
頭の中で誰かにレクチャーする
本当にその知識を自分のものにできているかを確認するために、誰かに説明することが効果的です。聞いてくれる人がいればいいですが、なかなかそういう人は見つかりませんし、わざわざ時間を取ってもらうのも手間です。
そこで、頭の中で好きな人に向かって説明してみることをお勧めします。頭の中の話なので、聞いてくれる人は聞いてもらいたい人や聞いている様子を想像しやすい人など自由に設定できます。
イメージをしやすい人を選べば、その人物が質問してくる所まで想像できることもあります。この人ならこんなことを聞いてきそうとか、この人は難しい言葉で説明しても聞いてくれないからわかりやすく説明しないととか、できるだけリアルに相手を想像して説明してみます。
この想像で相手に説明してみるのは、ある程度その分野について理解が深まった段階で「自分は本当に理解できているのか」というのをチェックする際に利用すると効果的です。自分でも全く分かっていない段階では説明することができずリアルにイメージできません。
わからないのは単語がわかっていないから
テキストや参考書を読んでいて全く頭に入ってこない、気が付いたら寝てしまっているってことはないでしょうか?私はよくありました。この状況を打開するのに効果的な方法は、「わからない単語を探す」です。
基礎からわかる勉強の技術という本があり、概略はこの本に書いてあります。子供でも読めるようにしてあるのでわかりやすいです。
要は、実は特定の単語の意味が全く分からないことで、全体がわからないような気がしているという話です。
その特定の単語というのを見つけ出し、その単語について徹底的に理解を深めると、文章全体がわからないような気がしていたのが一気に理解できるようになります。
まず、読んでいるだけで眠くなる箇所、頭がの中で糸がからまっているような気持になる個所が出てきたら一旦気持ちを落ち着けて「どの単語がわからないか」という確認作業を開始します。
そして、「この単語の意味が全くわからん!」という単語を見つけたら、その単語を理解することに全力を尽くします。その具体的な方法は先ほどご紹介した本に書いてあるので、もしよかったら買って読んでみてください。
4.独学は無理だと感じた方へ

テキストを読むだけでは全く理解できません…という人は
1.で説明したように、実務の経験もなくまっさらの状態から勉強を始める場合、テキストを読むだけでは全く理解できないという人もいると思います。
そういう人は、無理に独学で何とかしようとすることで本来の目的を達成できずただやった感だけで終わってしまう可能性も高いです。
もしあなたがそのような状況でそれでも独学で勉強しようとするメリットは「夢を実現できなかった時の言い訳ができる」というだけです。「お金がなくて独学でやるしかなかった」「時間がなくて独学でやるしかなかった」だから資格を取れなかった、という具合です。
もちろん、そこまで本気で資格を取りたいと思っていないのであればそれで何年も独学を続けるのもいいと思います。資格を取ることが目的ではなく、中小企業診断士の試験範囲の勉強をしたいだけで、そのモチベーションとして資格を目標としているという人もいるでしょう。
わからない時に誰かに聞ける、教えてもらえるありがたさ
効率よく勉強する方法として、誰かに頭の中に説明してみるというのをお勧めしましたが、逆に誰かに教えてもらうというのも非常に効果的な勉強方法です。独学はそれができずわからないことがあったら解決までに相当な時間がかかったりします。
最近はネットの力でピンポイントな情報収集もやりやすくなっているので独学の道は昔よりは楽になっていますが、人に聞くことほど自分の知りたいことがピンポイントで短期間に理解できる方法はありません。
通学でも通信講座でも、先生に質問ができるというのは非常に心強いメリットです。「自分はあまり質問するタイプじゃない」という方も、本で読むのと先生が説明するのを聞くのとでは理解しやすさがかなり変わってきます。
理解できるまでの時間を考えると、独学にこだわらなければならない理由はほとんどなくなってきます。
目先のお金に惑わされるな
独学の自信がない方は、同じぐらい時間的な融通が利く通信講座がお勧めです。
それでも、通信講座と独学でテキストを購入するのとでは金額が大きく変わってきます。そこに着目して、やっぱりお金がないから…と通信講座を敬遠してしまう人は本気で中小企業診断士になる気がないのだと思います。
中小企業診断士になって資格を生かした仕事を始めれば、比較的容易に年間数百万円程度は稼ぐことができます。営業力に自信がない方でも中小企業診断士協会に入会することで、時々1日○万円みたいな募集に応募することができます。
資格によってお金を稼ぐことができるのは、当たり前ですが合格してからです。独学で5年かかって合格できる人が、通信講座なら3年で合格できたとします。仕事を辞める年齢が同じだとすると、単純に2年分の売上金額を失うことになります。
しかも、その対象となるのは十分に事業が成長した最後の2年分です。というのも、駆け出しの中小企業診断士の1年目の売上というのはいつ始めても同じです。2年合格が遅れた人が、2年前から業務を始めた人の3年目と同額いきなり稼ぐことはありません。
最後の2年と言ったら順調にやっていれば個人事務所だったとしても1千万円程度稼げていても全く不自然ではありません。つまり、目先の数十万円を惜しんだばっかりに将来の2千万円を失っている可能性があるわけです。
それでも「お金がないからテキストを購入して独学で」というのは、資格を全く有効活用するつもりがないか、生涯合格する気がないか、いずれにせよ何のために資格取ろうとしているのかよくわからない人だけが得をする方法です。
通信講座でも独学の作戦は有効
通信講座でも先ほどお話しした効率的な勉強法は利用可能です。むしろ、体系的・網羅的なテキスト・カリキュラムがあった方が独自に参考書をあつめる独学に比べてより効果的です。
通信講座は、教材が体系的に準備されており、講師が講義してくれるという点、独学に比べて高額である点が独学と異なります。しかし、いつでも好きな時に講義を聴けますし、時間的な拘束は独学と同じです。
通信講座も広義では独学ととらえてもいいぐらいですが、この記事では独学は「完全に一人で参考書やネットの情報のみで合格を目指す人」としているため、あえて通信講座とは分けています。
このため、通信講座でも独学でも特に変わらない点については流用することができます。こうなってくると、通信講座の問題は単純に初期投資が独学よりかかるという点だけです。
お勧めの通信講座
ここまで読んで、「お金がかからない独学を考えていたが、通信講座の方がいい!」と思われた方もいるかもしれませんので、お勧めの通信講座について記載させていただきます。お勧めとして列挙させていただいていますが、あくまで私見ですので全ての講座で資料請求してみて一番自分に合ったものを自分の目で判断されることをお勧めします。
スタディング
中小企業診断士の通信講座から始まっている通信講座です。いまでは様々な講座がありますが、中小企業診断士講座は最も古いこともあり、充実した講座内容に定評があります。
まずは資料請求をしてみましょう。
クレアール
こちらは公認会計士の通信講座から始まった通信講座です。公認会計士と中小企業診断士は、試験としてはよく似ており、公認会計士の方が難しいです。この公認会計士を非常識合格法というキャッチフレーズで短期合格を目指すノウハウに定評があります。
こちらも下記バナーから資料請求してみることをお勧めします。
アガルートアカデミー
難関資格の通信講座として台頭してきているところです。サンプルを見る限りフルカラーテキストで余白も多く、使いやすい印象です。
資料請求は下記バナーからできるので、とりあえず資料請求しておきましょう。
診断士ゼミナール(旧レボ)
名前の通り中小企業診断士に特化した通信講座です。10年間診断士試験を研究したとあり、サイトやテキスト等は手作り感がありますが、特化型の通信講座という点で期待できます。
こちらも資料請求しましょう。
TAC
通学可能な拠点を持つ老舗の専門学校です。ブランドと実績から、総合力は高いです。多くの人が利用しているという点を重視する人には向いています。
LEC
東京リーガルマインドという元々は法律系の資格取得から始まった通学可能な拠点を持つ老舗の専門学校です。中小企業診断士の通信講座もあり、歴史も古いためノウハウの蓄積は期待できます。
こちらも資料請求しましょう。
5.最後にアドバイス
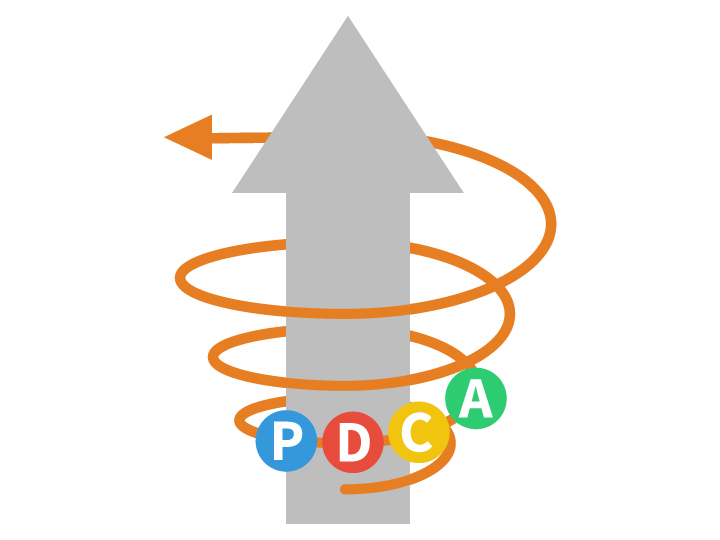
PDCAではなくDCAP
PDCAというのは、Plan(計画する)、Do(実行する)、Check(確認して改善点を探す)、Action(改善する)の頭文字で、これを何度も繰り返しながらよりよいやり方を模索していき、質を高めていく方法です。
しかし、計画するというのはともすれば頭でっかち、畳の上の水練、石橋をたたき壊すことになりかねません。つまり、あーだこーだ考えてばかりでなかなか実行に移せない状況です。
私はトライアスロンにチャレンジしようと思った時、まずはどうやったら大会に出れるのかを調べました。どういった大会があるのか、距離は、場所はとある程度調べて、まず最初に始めたのは走ることでした。
中小企業診断士の試験の話と何の関係があるのかと思われるかもしれませんが、試験勉強もまずは勉強してみることから始め、しばらく試行錯誤した後に計画を立てるべきだと考えます。
そうでなければ、正しく見積もることもできないし、何よりできない理由を考えてばかりで実行に移せなくなる恐れがあります。大切なことは小さな一歩をまずは踏み出してみることです。最初はがむしゃら、やみくも、何度もつまづくことになると思います。
そうして壁にぶつかって初めて、中小企業診断士試験に合格するとはどういうことなのかというのを真剣に考えます。
つまり、Doから初めて、Check、Actionをやって壁にぶつかってからPlanです。トライアスロンの話に戻りますが、私は最初がむしゃらに走ってまずはフルマラソンに出ました。それなりに練習したので4時間を切ることができましたが、それよりも速く走れなければトライアスロンでは心もとないと思いました。
そこで、フルマラソンを3時間台の前半で走るにはどうすればいいのか真剣に考えざるを得なくなりました。そうなると、普段全く意識していなかった「そもそも走るってどういうこと?」と走る動作そのものについて改めて考える必要に迫られます。
目標が高ければ高いほど「そもそもそれってどういうことなんだろう?」という深掘りが必要になってきます。そうなる前にあーだこーだ頭で考えていてもなかなか前に進みません。
普段何の意識もせずにできることについては、人は考えません。無意識に任せた方が楽だし効率がいいからです。しかし一度それより高いレベル、意識しなければ到達できないレベルを目指し始めると考えざるを得なくなります。
この、考えざるを得なくなる状況になるにはある程度実践してみる必要があります。この記事では、勉強のやり方も含め、独学で合格するにはどうすればいいのかを説明しましたが、まずは我流でいいので勉強を始めましょう!話はそれからです。